お電話でのお問い合わせ
EDUBALでは、海外在住の生徒様ならではのお悩みと真摯に向き合い、指導させていただきます。
03-6756-8620
電話受付 平日10:00~19:00 (日本時間)
EDUBALでは、海外在住の生徒様ならではのお悩みと真摯に向き合い、指導させていただきます。
03-6756-8620
電話受付 平日10:00~19:00 (日本時間)
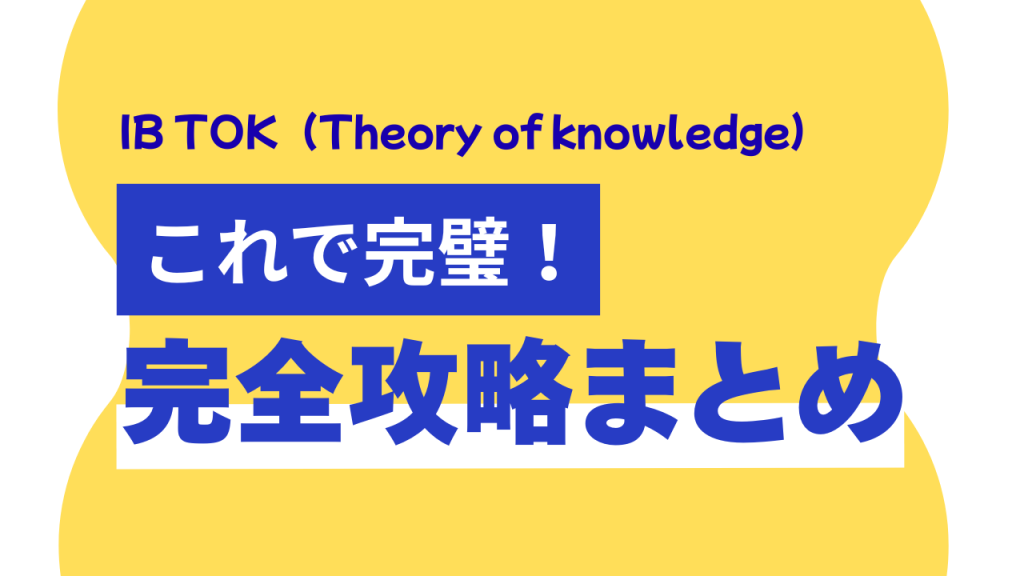
IB経験者のEDUBAL教師による情報をもとに、TOKの全体像、学習内容、評価項目などに関するアドバイスを集めました!
どのようにTOKの対策をすればいいのか分からない!」「エッセイとプレゼンのテーマが決まらない…」などのお悩みをお持ちの皆様、是非このページをお役立てください!
本記事は全て国際バカロレア機構『知の理論(TOK)ガイド』(2022年)より引用した公式の情報に基づいております。
.
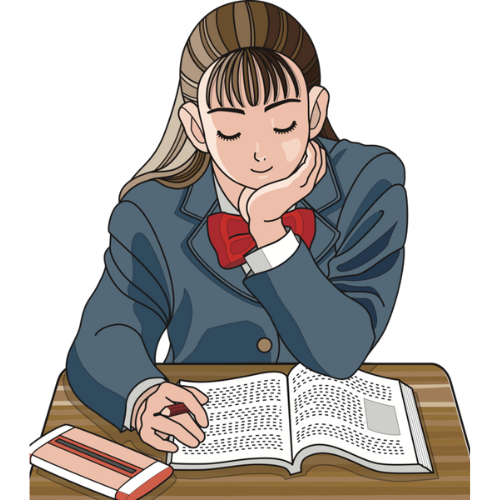
TOK(Theory of Knowledge/知の理論)は、IBディプロマ・プログラムのコア科目のひとつで、「批判的に思考して、知るプロセスを探究する授業」です。特定の知識を覚えるのではなく、「私たちはどうやって『知っている』と言えるのか?」という問いを考え続けることが目的です。TOK指導の手引きにも、次のように説明されています。
「『知の理論』(TOK)は、批判的に思考して、知るプロセスを探究する授業です。特定の知識体系を身につけるための授業ではありません。DPの『コア』の必修要件の1つとして、DPを履修する生徒全員が取り組みます。」
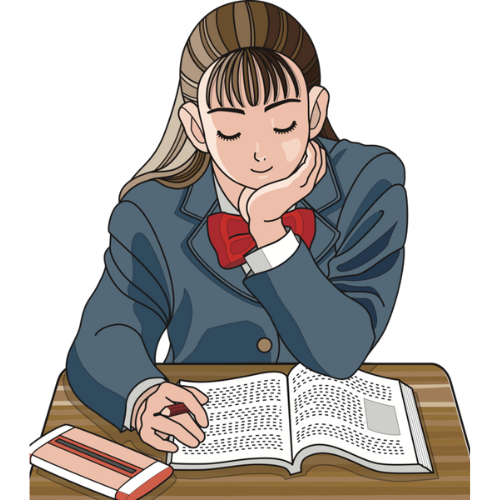
主に以下の5項目に狙いを定めています。
1. 知識の構築に対する批批判的なアプローチと、教科学習、広い世界との間のつながりの発見
2. 個人やコミュニティーがどのようにして知識を構築するのか、その知識がどのように批判的に吟味されるのかについて、認識の発達
3. 文化的なものの見方の多様性や豊かさに対して関心を抱き、個人的な前提や、イデオロギーの底流にある前提の自覚
4. 自分の信念や前提を批クリティカル判的に振り返り、より思慮深く、責任意識と目的意識に満ちた人生の形成
5. 知識には責任が伴い、知ることによって社会への参加と行動の義務が生じることへの理解
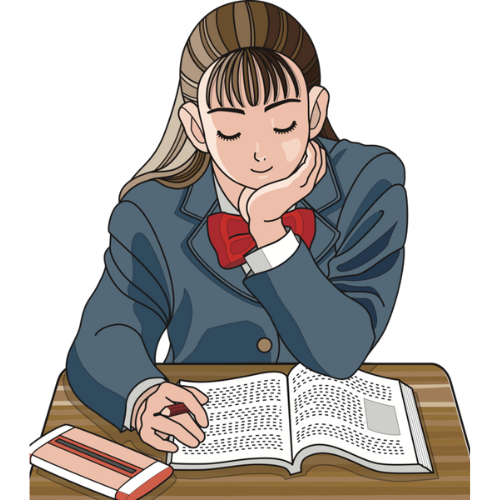
主に以下の7つの能力を身につけることを目標としています。
1. 「知識に関する主張」を裏づける目的で使用されているさまざまな種類の正当化の根拠を特定し、分析する力
2. 「知識に関する問い」を提起し、評価し、答えようとする力
3. 学問領域や「知識の領域」がどのようにして知識を生成、形成するかを考察する力
4. 「共有された知識」と「個人的な知識」を構築するプロセスで「知るための方法」が果たす役割を理解する力
5. 「知識に関する主張」「知識に関する問い」「知るための方法」「知識の領域」の間のつながりを探究する力
6. さまざまなものの見方を認識して理解し、自分自身のものの見方に関連づける力
7. プレゼンテーションで、実社会の状況をTOKの視点から探究する力
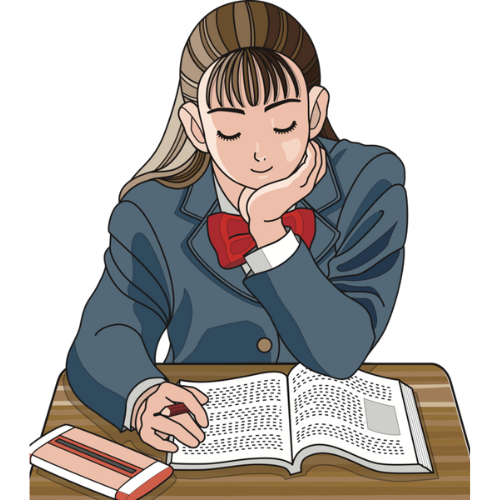
TOKでは、「知識」を大きく2つに分けて考えます。
1つ目:「共有された知識(Shared Knowledge)」
社会的に構築された知識で、学問分野や文化的伝統などに見られる知識のこと。それは複数の人々が協力して作り上げ、検証し、時間とともに進化していきます。例:物理学・歴史学・芸術・倫理など。別に、「私たちは知っている(We know)」という形で表されます。この知識は、社会全体で共有される客観的な知識体系であり、学問的な検証(査読や再現性)を経て信頼されます。また、文化や宗教の違いによっても異なる形で共有されるため、「知識は文化を超えられるのか」という問いが生まれたりもします。
2つ目:「個人的な知識(Personal Knowledge)」
個人の経験、練習、感覚、価値観に基づく知識のこと。例えば「どのようにピアノを弾くか」「どのようにスフレを焼くか」といった手続き的知識(procedural knowledge)も含まれる。この「個人的な知識」は言語化が難しく、他者と共有するのが難しいことが多いです。別に「私は知っている(I know)」という形で表されます。個人的な知識は時間とともに変化し、経験を通じて成熟していきます。個人の視点(perspective)は、この知識によって形づくられ、逆に社会的知識からも影響を受けます
「共有された知識」と「個人的な知識」は相互に影響し合います。
たとえばアインシュタインの理論は、彼の個人的な洞察(個人的知識)から生まれましたが、それが物理学(共有された知識)の一部として認められるには、科学的な検証を経る必要がありました。逆に、学問や文化などの共有された知識は、個人の見方や思考にも影響を与えます。
TOKではこのバランスの取り方が大切です。
個人的視点に偏りすぎると主観的になり、共有知識に偏りすぎると無機質な分析に陥ります。
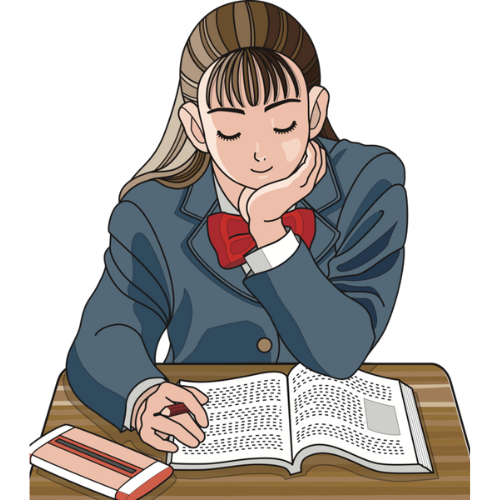
TOKでは、二階の主張を中心に扱います。
つまり、「知識とはどう作られ、どう評価されるのか?」という問いそのものを探究するのです。
| 一階の主張 | 各学問内での事実的な主張のこと。例:「素数は無限に存在する」 |
|---|---|
| 二階の主張 | 知識そのものについての主張のこと。例:「数学的知識は確実性が高い |
TOKの中心となるのが「知識に関する問い(KQ=Knowledge Question)」です。
これは特定の事実ではなく、知識の性質・信頼性・根拠を問う一般的な問いです。
| 良い例 | 「医学において、どのようにして因果関係を知ることができるのか」 |
|---|---|
| 悪い例 | 「プラシーボ効果はどのように機能するか」 |
良いKQ(Knowledge Question)の特徴
・知識そのものについて問う 例:「私たちはどのようにして何かを知っていると判断するのか?」
・単一の正解がなく、複数の合理的答えがありうる(オープン・クエスチョン)
・学問固有の専門語ではなく、一般的な言葉で表現する
どうでしょうか?改めてTOKについてしっかりと理解をすることで、より良いTOKエッセイ&プレゼンテーションができそうですね!
TOKは「正しい答え」を探す授業ではなく、「なぜそう考えるのか」「どう知っていると言えるのか」を問い直す授業です。「知識の領域(AOKs)」や「知る方法(WOKs)」を使って、世界をより深く、多面的に理解していく力を培っていきましょう!
.
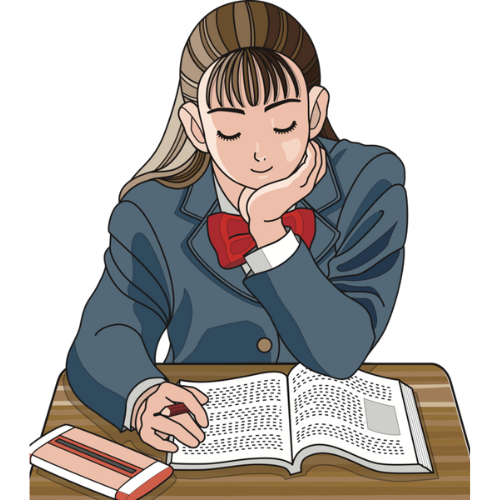
TOKは主に以下の8つの手段によって“私たちは知る”と考えています。
①言語、②知覚、③感情、④理性、⑤想像、⑥信仰、⑦直観、⑧記憶
生徒は、8つある「知るための方法」を幅広く探究し、そのうち4つを重点的に学ぶことが推奨されています。これらは「私たちはどのようにして知るのか」「私はどのようにして知るのか」という問いに答えるための概念的ツールであり、知識を理解・構築する助けとなります。TOKでは、各方法を個別に学ぶのではなく、異なる「知識の領域」でどのように機能し、個人的・共有的知識の形成にどのように影響するかを関連づけて探究することが重視されています。
①言語
言語は、人間が複雑な意思疎通を行うための心的能力、またはその記号体系そのものを指します。文字や音声、ジェスチャーなど多様な「記号」に基づき、思考や知識を伝達・構築する役割を持ちます。言語は日常生活に不可欠である一方、曖昧さや翻訳の問題なども伴います。また、言語は単に世界を描写するだけでなく、経験や知識そのものを形づくると考える立場もあり、これは「言語決定論」と呼ばれます。
②知覚
知覚は、私たちが外界についての知識を得るためのプロセスで、伝統的には五感によるものとされますが、近年は痛みやバランス感覚なども含まれると考えられています。知覚がすべての知識の基礎とされる一方で、知覚には事前の概念や期待が影響するとする見方もあります。現在では、知覚は受動的ではなく、概念的枠組みに基づいて世界を解釈する能動的なプロセスであると広く理解されています。このため、私たちが世界を「ありのままに」知覚しているのかどうかには議論があります。
③感情
感情は、生理的な反応として自然のプロセスから生じるという自然主義的な見方と、社会的・文化的文脈によって形成されるという社会構築主義的な見方の両面があります。ダーウィンは感情を普遍的な生理現象と考えましたが、文化固有の感情も多く存在します。また、感情はかつて理性を妨げるものと見なされましたが、近年では社会・倫理・政治などの知識を理解するうえで重要な役割を果たすと考えられています。
④理性
理性とは、感覚的経験を超えて論理的に物事を理解する能力であり、前提から妥当な結論を導く推論と深く関わっています。ただし、理性による推論は常に厳密ではなく、文化や知識の領域によって合理性の基準が異なる場合もあります。推論には、具体的事例から一般的結論を導く「帰納的推論」と、一般原理から具体を導く「演繹的推論」があり、特に帰納的推論は自然科学や人文・社会科学で重要な役割を果たします。
⑤想像
想像は、感覚的経験を経ずに心の中でイメージや概念を形成する能力であり、創造性や問題解決、理論構築などと深く関係しています。近年では「〜ということを想像する」という命題的想像にも注目が集まっています。想像は科学や芸術で重要な役割を果たす一方、主観的で信頼しにくい面もあります。また、「もしも〜だったら」と考える反実仮想や、可能性の探求にも関わり、道徳教育や共感、自己理解の向上にも寄与するとされています。
⑥信仰
信仰は一般に宗教的な文脈で使われますが、「確信」という非宗教的な意味でも用いられます。多くの宗教では信仰が神や聖典への信頼に基づきますが、仏教や人道主義のように必ずしも有神論に依らない形もあります。信仰は理性と対立するものと見なされることもありますが、両者は相互に依存するという立場もあります。信仰はしばしば証拠を超えた確信として理解され、証拠に基づかない知識のあり方として批判や議論の対象となっています。
⑦直観
直観は、推論や証拠を用いずに、直接的かつ即座に「知る」能力を指します。ユングはこれを「無意識を経る知覚」と説明しました。直観は本能や先天的知識と関連づけられることもあり、倫理における善悪の判断や科学的発見にも関わるとされています。直観的な判断は根拠を伴わないことが多いものの、瞬間的な洞察として価値を持ちます。一方で、直観は独立した知の方法ではなく、経験・知覚・想像など他の要素の組み合わせにすぎないとする見方もあります。
⑧記憶
記憶は、私たちが保持する知識の大部分を形づくるものであり、「個人的な知識」の形成に深く関わっています。知覚が現在を、想像が仮想を扱うのに対し、記憶は過去に起こったと信じる出来事を対象とします。記憶は単なる知識の保管庫ではなく、新しい状況の理解や判断にも影響を与える能動的なプロセスです。しかし、記憶は感情や主観に左右されやすく、その信頼性が問題視されることもあります。それでも私たちは日常的に記憶に依存し、多くの場合それを信頼しています。
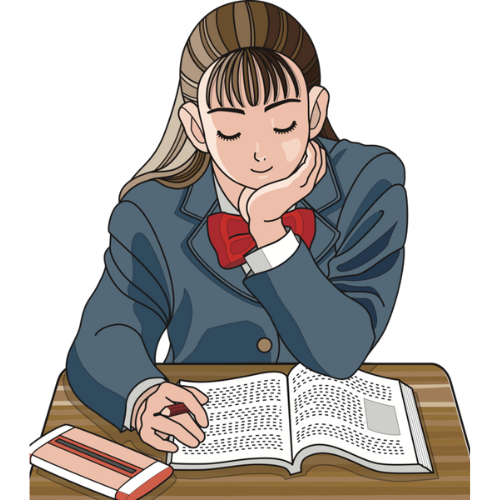
よく知っていますね!TOKは、以下の8つの「知識の領域」を設定しています。
①数学、②自然科学、③ヒューマンサイエンス(人間科学)、④歴史、⑤芸術、⑥倫理、⑦宗教的知識の体系、⑧土着の知識の体系
生徒は、8つの「知識の領域」を幅広く探究し、そのうち6つに重点的に取り組むことが推奨されています。これらの領域は、知識の性質や構築の仕方を多面的に理解するための枠組みです。TOKでは、単に領域を学ぶのではなく、自分が履修しているIB科目──例えば化学、地理、ダンスなど──の学習を通して、それぞれの科目における「知識の本質」や「知るということのあり方」について考察することが重視されています。
①数学
数学は、公理と演繹的推論によって成り立つため、高い確実性を持つ知識の領域です。同時に、問題解決や新しい理論の発見には想像力も求められ、非常に創造的な側面を持ちます。さらに、自然科学や人間科学の探究を支える基盤であり、芸術とも密接に関わっています。
②自然科学
自然科学は、自然界の法則や因果関係を発見しようとする学問で、観察や実験を通して客観的で経験的な知識を追求します。人間の主観を排除しようとする点が特徴であり、仮説検証を重視します。また、「科学的」と「非科学的」を分ける基準や、科学的知識が他の領域より信頼される理由もTOKでの重要な探究テーマです。
③ヒューマンサイエンス(人間科学)
ヒューマンサイエンス(人間科学)は、人間の社会的・文化的・生物学的側面を探究する学問で、心理学や経済学、人類学などが含まれます。自然科学と同様に科学的方法を用いますが、人間の行動には例外が多く、普遍的な法則を見出すことが難しいため、統計的手法に依存します。その結果、生成される知識は自然科学に比べて予測の信頼性が低い傾向があります。
④歴史
歴史は、過去の出来事を記録と証拠をもとに探究する「知識の領域」であり、人間の行動を理解する手がかりを提供します。しかし、文献証拠の信頼性や、事実がどこまで客観的に語れるのかには議論があります。歴史学者の視点や時代背景が証拠の選択や解釈に影響を与えるため、歴史的知識には主観性が伴う点が特徴です。
⑤芸術
芸術は、視覚・舞台・文芸などの創造的表現を通して人間の経験や現実を探究する「知識の領域」です。感情と理性の両方を用いて個人的な意味を創造しつつ、社会的・文化的メッセージを発信する役割も果たします。芸術は「個人的な知識」と「共有された知識」をつなぐ架け橋であり、内省や社会的気づきを促す重要な手段とされています。
⑥倫理
倫理は、「何が道徳的か」を知ることが本当に可能かという問いを中心に展開される「知識の領域」です。道徳的規則の存在や、それに従うことが本当に正しいのかが議論の焦点となります。また、道徳的価値を判断する際に「行為の結果」と「動機」のどちらを重視すべきか、人間の本性は利他的か利己的かといった問題も探究の対象です。
⑦宗教的知識の体系
宗教的知識の体系は、人生の意味や目的などの根本的な問いに答えを与える「知識の領域」です。有神論から多神教まで多様な信念を含み、「共有された知識」と「個人的な知識」の両側面を持ちます。宗教は人々の世界観や倫理観に深く影響し、他の知識領域の理解にも関わります。そのため、宗教的議論は慎重さを要しつつも、TOKにおいて重要な探究対象となります。
⑧土着的知識の体系
土着の知識の体系は、特定の文化や社会に根ざしたローカルな知識を探究する「知識の領域」です。これらの知識は固定的ではなく、外部の文化的影響を受けながら絶えず変化しています。例えば、マオリ族の知識体系は伝統と西洋文化の要素が融合しています。TOKでは、こうした多様な土着知識の意思決定や思考のプロセス、全体的な世界観を理解することが重視されます。
.
一通りTOKの全容について理解ができたところで、実際にどのような評価基準なのかも、評価内容を具体的に見ていきましょう!
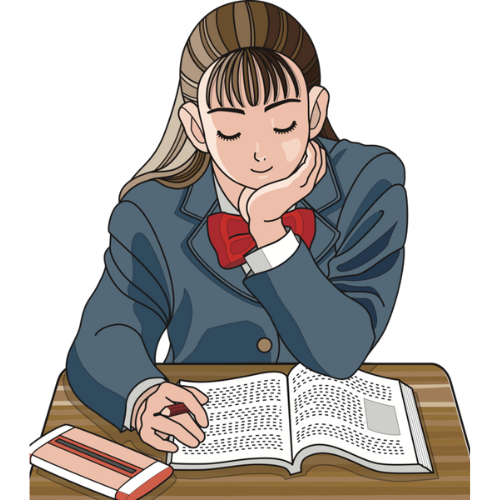
TOKには主に「TOKエッセイ」と「TOKプレゼンテーション」という2つの評価軸があります。
それぞれ、下の図のような評価内容になっています。
| パート1:TOKエッセイ (Prescribed Title Essay) |
パート2:TOKプレゼンテーション(Presentation) | |
|---|---|---|
| 内容 | IBが出題する6つの「所定課題」から1つを選び、1600語以内(日本語3200字以内)で論述。 | 個人または最大3人グループ。実社会の状況を題材に「知識に関する問い(KQ)」を探究。1人あたり約10分。 |
| 配点 | 10点(全体の67%) | 10点(全体の33%) |
| 評価者 | 外部評価(試験官) | 内部評価(教師)+モデレーション |
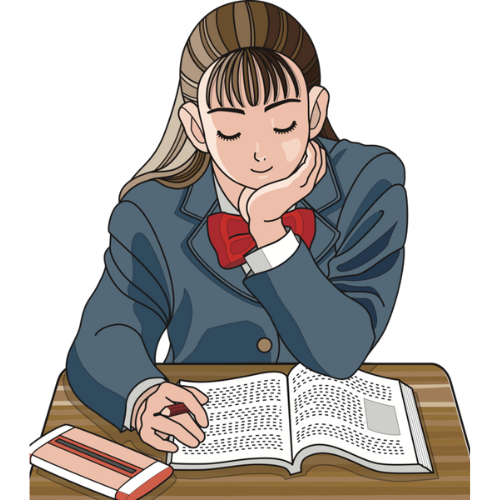
・概要
まずTOKエッセイの評価は、相対評価ではなく絶対基準評価に基づいて行われます。つまり、他の生徒との比較ではなく、あらかじめ定められた基準にどの程度達しているかが判断されます。また、評価は「分析的に項目を足し算する方式」ではなく、全体的印象(global impression)に基づく包括的な判断によって行われます。採点は5段階レベル(Level 0〜5)で行われ、各レベルには「典型的特徴」と「可能性のある特徴」が示されています。これらはチェックリストとして用いるものではなく、全体的判断の参考として活用されます。
| TOKエッセイの目的 |
|---|
| ・「知識に関する問い(Knowledge Question)」を中心に、8つの知識の領域や8つの知るための方法を結びつけて思考を展開。 ・実社会の事例をもとに論理的議論を展開することが重要。 ・研究論文ではなく、「TOK的思考」の深さと構造が評価対象。 |
| 語数・形式 |
|---|
| ・1600語以内(日本語3200字以内) ・ダブルスペース・12ポイントフォント ・脚注・参考文献・図表は字数に含まれない ・超過した場合は「読まれない+減点(−1点)」 |
| 学問的誠実性 |
|---|
| ・剽窃禁止(引用・参考文献の明示が必須) ・引用形式は自由だが、著者名・発行年・題名・ページ数などを明示 ・一般常識以外の情報には出典を付けること |
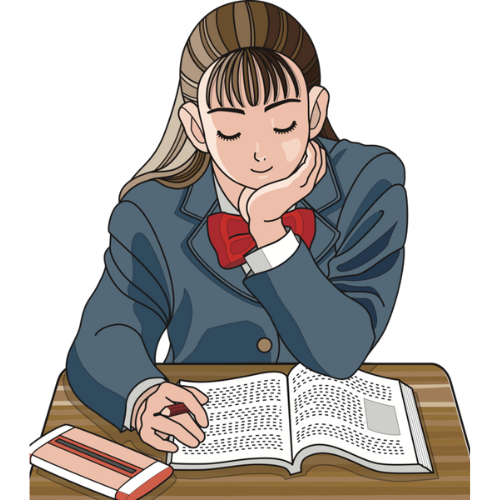
・概要
TOKプレゼンテーションでは、まず実社会の状況(RLS: Real-life situation)を出発点とし、そこから知識に関する問い(KQ: Knowledge Question)を導き出して分析を行います。分析には、TOKの主要な概念や枠組みを用いることが求められます。発表は授業中にライブ形式で実施され、録画映像のみの提出は認められていません。発表は個人または最大3人までのグループで行うことができ、各生徒はTK/PPD(Presentation Planning Document)を作成し、評価の一部として提出する必要があります。
| TOKエッセイの目的 |
|---|
| ・「知識に関する問い(Knowledge Question)」を中心に、8つの知識の領域や8つの知るための方法を結びつけて思考を展開。 ・実社会の事例をもとに論理的議論を展開することが重要。 ・研究論文ではなく、「TOK的思考」の深さと構造が評価対象。 |
| 語数・形式 |
|---|
| ・実社会の状況の説明 ・中心となるKQ ・実社会の状況とKQのつながり ・論の展開・二次的KQの扱い方 ・結論と社会的意義 ・500語以内(日本語1000字以内) ・図解の使用可、ただし2ページ(表裏)以内。 |
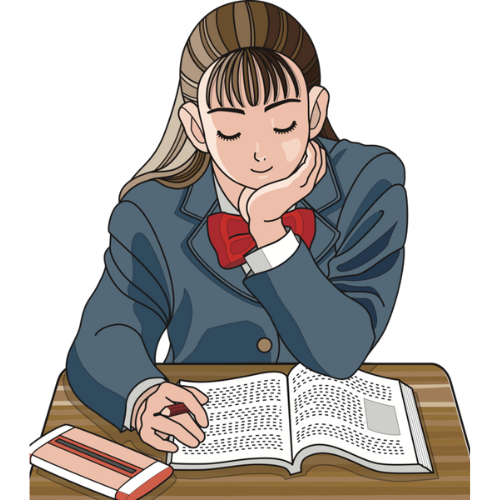
EDUBALは難関大学に通う帰国子女や元IB生の大学生教師と、家庭教師を探している現役IB生やPre IB生をつなぐオンライン家庭教師サービスです。
EDUBALでは、インターネットのビデオ通話を通して授業を行うため、世界中どこにいても授業を受けることができます。また、帰国子女大学受験を経験している教師も多く在籍しています。
これまでにも、
・国内大学IB入試出願のためのサポートをしてほしい!
・苦手科目対策をしたい!
などのお悩みを抱えた生徒さまに、IBを経験した大学生の教師をご紹介し、
オンライン家庭教師の指導によってIBの勉強のサポートをしてきました。
EDUBALには約600名のIB経験者の大学生が教師登録をしています。
実際にIBで高得点を取得した教師が、自らの経験に基づいてIBの勉強をサポートいたします。
東京大学や京都大学をはじめとする国内外の難関大学に通っている教師や、IBで40点以上を取得している教師も多く在籍しています。
実際に、EDUBALを受講した方からは、
「実際にIBを経験した方だったので、的確な指導をしてもらえた上に、日本語で教えていただけたことで今まで分からなかった点が理解できるようになりました。」
「担当の先生も過去に私と同じように英語力に悩んでいた経験があり、同じ悩みを抱えていた先生から指導を受けることができたのでとても参考になりました。」
といった声をいただいています。
現在、無料体験授業も実施しておりますので、IBや国内外の大学進学でお困りの皆さん、まずはEDUBALにご相談ください!

【先輩IB生の体験談も掲載!】
国際バカロレアって何?という方のための「IB丸わかりBook」を作成しました。
IBって何を勉強するの?
IBを取るべきか迷っている…。
IBはどこで学べるの?
などの疑問にお答えします。
ダウンロードは無料です!

竹迫 先生(Imperial College London / Faculty of Natural Science)
竹迫 先生(Imperial College London / Faculty of Natural Science)
滞在国
アメリカ・カナダ・イギリス
担当コース
経験豊富で、明るく熱意のある教師です。自身の経験から説明を聞くばかりでは知識の定着がしづらいと考えており、双方授業を通じて生徒様自身に問題を解説して頂くといった方法から理解度を測りつつ指導をすることを心掛けます。
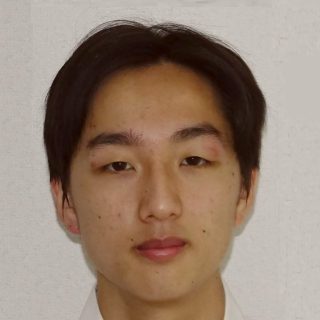
吉田 先生(東北大学 / 工学部)
吉田 先生(東北大学 / 工学部)
滞在国
ドイツ
担当コース
温厚で笑顔の多い教師です。生徒様とのコミュニケーションを大切に目標を共有しながらその時々に合った指導をしていきます。授業では基礎を重点に置き、一つ一つ積み重ねながら応用へと繋げていきます。

五十嵐 先生(国際基督教大学 / 教養学部)
五十嵐 先生(国際基督教大学 / 教養学部)
滞在国
スイス・オーストリア・フランス
担当コース
笑顔が多く人懐っこい印象で親しみやすく熱意のある教師です。生徒様の状況把握と事前準備をしっかり行い、できる限りの結果を出せるよう、寄り添ったサポートを目指します。海外経験が豊富でコミュニケーションの能力も高く、楽しくわかりやすい授業を心掛けます。
※他の科目について、もっと詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。
下記では、今までEDUBALで指導を受講された生徒様、保護者様から寄せられた声を掲載しています。
EDUBALで家庭教師をつけるかどうか迷われている方は、ぜひ参考にご覧ください。
この度はご指導いただき、ありがとうございました。初めてのオンライン家庭教師でしたが、想定以上に息子は有益に、また楽しく感じたようで、毎回授業に前向きに取り組んでおりました。宿題も適切に出していただき、モチベーションにもつながっていたようです。また機会がありましたら、よろしくお願い申し上げます。
明るくハキハキとした丁寧な授業で、毎回有意義な時間を過ごすことができたようです。メールでのコミュニケーションも丁寧で信頼できました。
授業内では、自分が分からなかった部分を図などを用いて丁寧に自分がわかるまで掘り下げて頂き助かりました。また、授業内でとったノートなどを授業後に送ってくださり、後で読み直した時に理解しやすくとても助かりました。
毎度毎度授業が楽しみです。モチベーションが下がる時も元気をいただいております。
IB受験の論文の書き方と模擬面接について丁寧に教えていただき、息子本人が面接と論文に関してもっとわかるようになり、大分自信がついたようでした。今回は主に論文の書き方について指導してくださいました。レッスン終了後、前より書く字数も増えましたし、自分の意見もちゃんと段落を分けて、文章のなかに表現できるようになったと思います。時差があるなかで、毎日朝早くご指導いただいて、ありがとうございました。